紙の日記を書けているかどうかは自分にとって、セルフケアができているかどうかの目印だ。とすればいまは、ごく軽いセルフネグレクト状態に突入していることになる。日記なんて何週間も書けていない。なんなら衣替えもできていないし、本棚の整理もできていない。本は勝手に増える。定期的に整理をしないと大変なことになる。だからいまは、大変な状態ではある。
秩序と無秩序について考えている。
たとえば部屋の掃除をする。満足いくまできれいにしたとする。「やったー!」となる。しかしまた暮らしているうちにホコリは溜まるし、ゴミも落ちるし、風通しの悪い家具の裏にはカビだって生えるかもしれない。じゃああの「やったー!」は徒労だったのかというと、決してそんなことはない。掃除を終えて「やったー!」と思ったあのとき、部屋のなかには確かに秩序が生まれたのだ。大事な大事な秩序。やがて壊れることは確定している、けれどその瞬間の自分にとってはかけがえのない秩序が。
漱石の『道草』の最後の場面で、たびたび金の無心に来る養父との問題がようやく解決したとき、主人公の妻のお住は「ええ安心よ。すっかり片付いちゃったんですもの」と言う。ところが主人公の健三は「世のなかに片付くなんてものは殆どありゃしない」と言う。僕は『道草』を扱った研究室のゼミのコメントシートに、「実際、片付くものなんて世の中にはほとんどない」と書いたのをいまでも覚えている。健三派だ。健三派であるところの僕はあのとき、確かに真実を言っていた。しかし真実では人は救えない。「片付いた」という感覚は幻想だ。でもその幻想こそが人には必要なのだろうと、いまだ自分の部屋に出ている夏仕様の服たちを見て思う。僕のコメントシートは院生のOさんが読んでくれたはずで、彼女はそのときなんと思ったんだろう。バカだなと思ったのかもしれない。
会社組織というのも、無秩序に秩序を持ち込もうとすることで駆動している。僕がいるのはデジタルマーケティングの会社だから特にそうなのかもしれないが、「業務の属人化を防ぐため、フローはなるべくマニュアルに残しとこう」「自動化できることはなるべくしよう」みたいな動きはつねに推進されている。みんなそうやって、きたるべき無秩序に備えて秩序を作っておこうと努力している。それでも人が入れ替わるタイミングやプロジェクトが激しく動くタイミングで、必ず大小の事故は起きる。でもその事故は、先人たちの秩序への意思がなければもっと大きな事故になっていたかもしれない。原理上、秩序というのは無駄にはならない。「無駄かどうか」を僕たちは確定できない。
世の中には、一方に「ノイズが大事」とか「安定はつまんねー」とか言う鼻持ちならないカルチャー系の人たちがいる。で、他方には「暮らしが大事」派の人たちがいて、彼らはやはり牧歌的なのを重んじている。……と、こういうふうにまとめると、まるで世の中では無秩序派と秩序派が対立しているように見える。が、実際には秩序と無秩序というのは繰り返されているわけで、その中のどっちかを切り取って「どっち派」みたく言うことに僕はやはり意味を感じづらい。きのこたけのこ論争と同じようなものに見える。どっちも食べればいいじゃんと。そこで「こっち派」と決めて言いきることは、ひとつの美学でもあるんだろうけど、あいにく僕はそういう美学がない。二元論で単純化しないでよ、と思う。むしろそればかり思っている。
結論はないのだけど、とにかくいまの僕にとっての問題は『現代人第五号』の原稿という無秩序と、その作業によって遅延され続ける「衣替え」と「本棚」という無秩序だ。まあ原稿については今週末ですべて集まりきるはずなので(俺の分も含めてだが、メンバーの分も。まじ頼む)、あとはこれを秩序立った形に整えてくれるのはデザイナーさんなんだけど。「最後に秩序を作る」ってのが一番大変な仕事なので、デザイナーさんってすごいなあと思う。あと『第五号』の僕の担当部分はインタビュー、座談会、小説、詩で、なんかいろいろむやみに書き散らしているんだけど、通底するひとつのテーマが「秩序と無秩序」だったりする。世はむずいことばっかりだ。それでもやっていこうぜ、みたいな、そういう感じ。
眠いのでそろそろ、覚醒という無秩序のなかに、睡眠という秩序を導入する準備をする。最初に書いた「やったー!」というのは睡眠にも当てはまる話で、「いろいろあったけど今日もとりあえず眠りにつけて嬉しいな」とか思うことは大事なことなのだ。そりゃそうだろって感じかもしれないけど、当たり前のことほど難しいよね。という話。


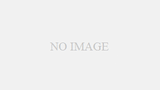
コメント