ラランドのサーヤという人は時折、「○○って意味ないじゃん!」という言い方をする。「ないじゃん?」という共感を求める問い方ではなく、「ないじゃん!」という言いきりで。「ない」の二音ではなく、「意味」という二音に思いっきりアクセントを置いた言い方で。どうしたって僕はそこに共感する。
もちろんサーヤのそれはあえて露悪的に振る舞ってみせる種類のボケなわけだから、相方ニシダのツッコミ待ちの発言である。けれどやっぱり、たとえば礼賛の音楽を聴くにつけても、ラランドのYouTubeでXやThreadsに対して高らかに「終わり」を告げる様を見ても、どこからどう考えてもサーヤはものごとに「意味」を求める人で、またその「意味」というのは彼女にとって、「かっこよくありたい」「センス良くありたい」といった美意識と切り離せないもののように見える。
意味とは呪いだ。人間が人間である以上、必ず誰かが戦わなければいけないたぐいの。意味について考え込まずに済む人ばかりなら、哲学なんてジャンルは成立していないだろう。
米津玄師の「Plazma」は、「もしもあのとき改札の前で立ち止まらずに歩いていたら、今こんなに傷だらけではなかったかもしれない」というような「if」を繰り返し歌う。僕はこれにも泣けてしまう。一昔前のノベルゲームのように、人生にはさまざまな分岐があって、バッドエンドに繋がるほうばかりを選んで辿り着いたのが「今」だと捉える。ないはずの意味を読み込んで、この「今」を、ドラマ仕立てに嘆いてみせる。
もちろん「Plazma」はポップソングだから、というより米津玄師は世のあまねく呪力を背負い込もうとするポップスターであろうとしているから、この歌は「今」を否定する作りにはなっていない。分岐はあくまで可能性の話であって、ifの世界線なんて本当は存在しない。かくして意味による絶望は、意味によって救済される。
意味なんてものにたぶらかされることがなくなりたい、と思う。意味は、意味を感じなくて済むようになるために存在する。戦いというものが、戦いについて考えずに済むようになるために存在しているように。
僕が今年に入って一番読んでいる/観ているのは、小谷野敦の本と鹿島茂のシラス講義である。それは彼らの、あらゆる些末な意味を超越したような境地に辿り着きたいからだ。そんなのじゃ宗教書を読む態度と変わらないじゃないかと人は言うかもしれないが、まあそのとおりだ。僕は小説も音楽も批評も、宗教書を読むようにして受け入れてきたし、だからこの点においても、自分がスピっていることをネタにするサーヤの感覚を勝手に分かったような気になっている。
サーヤにとってニシダという圧倒的な「無意味」が存在するように、無意味はじつは日常のそこかしこに溢れていて、それらに心底苛々したり、逆に救われたりもしながら生きている。飲み会だとか人付き合いだとか、意味がなさすぎて心底苛々するけれど、きっとそんなのに救われる日だって来るだろう。最悪なプラズマが、すでにとっくに目の前をぶち抜いている以上は。


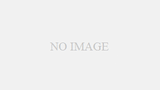
コメント